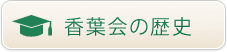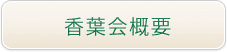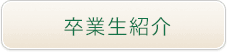■短大国文科の思い出 ~岩佐壮四郎~
岩佐 壮四郎
■関内にできた新しいキャンパス開設とともに、文庫キャンパスの国際文化学部も、社会学部と一緒に、釜利谷の地を去ることになった。大学が新しく出発をすることは、喜ばしいことだが、また様々の思い出の詰まった場所を離れることには、いささか寂寥の思いもないわけではない。わたしは、2017年3月に定年で退職するまで、関東学院に38年ほど勤務したうちのほぼ半数にあたる時間を、釜利谷キャンパスで教員として過ごしたが、以下、短大国文科が幕を閉じ、文学部比較文化学科(現・国際文化学部、比較文化学科)が誕生した当時の記憶と記録を、はなはだ恣意的、断片的ながら綴ってみたい。
■比較文化学科の誕生と短大国文科の終焉
■2002年4月、比較文化学科は最初の新入生を迎えることになった。
改組によって、短大の国文科と、文学部の一般教育担当の教員が中心になって比較文化学科が誕生、2002年4月新入生を迎えることになったわけである。石川康文文学部長と共に、比較文化学科の誕生に尽力された、テルさんこと小林照夫先生(学科長、その後文学部長)を中心に一般教育から佐藤佑治、佐藤茂樹、大内憲昭、尾形国治、藤原玲子、文玉任、永田俊勝、短大のほうは、一般教養(共通科目)から矢嶋道文、大越公平、国文からは伊東光浩、富岡幸一郎の各先生が移籍、このほか、外部から横田洋一、山口俊章の両教授が加わった。
■設立には紆余曲折があったが、その経緯については省略するとして、短大の解体と、人間環境学部の設立と共に、文学部における比較文化学科の誕生は、文学部にとってだけでなく関東学院大学の永い歴史のなかでも、特筆すべきものだったといっていいだろう。
もともと、夜間で共学の短大に、経済学部・工学部・神学部を加えて、戦後新制大学としてスタートした関東学院大学の教養部を母体に、英文学と社会学の領域をカバーしながら展開してきた文学部にとって、第3の学科を加えることは、1970年代初頭に出発した文学部にとって、永年の懸案だった。21世紀という新しい時代を迎え、グローバル化を視界に収めた比較文化学科の新設はその懸案が実現されることを意味していたからである。また、短大や文学部の改組は、法学部の新設と共に、人文・社会・自然の三領域をカバーする都市型総合大学として新しく「発展」、8学部からなる現在の体制のそもそもの出発点となったからでもある。
小林先生をリーダーに歩み始めた新学科には、担当教員の専門とする領域と、それに対応するカリキュラムの作成から、関連図書の選定などから必須科目の第二外国語のクラス分けに至るまで課題が山積みだった。教務課長を兼務していた槌谷事務次長と協力しながら、大内・佐藤(佑)・佐藤(茂)など、文学部の共通科目担当の先生たちが心血を注いだこれらのほか、新しく設けた宿泊オリエンテーションや学芸員課程の準備・実施などには、矢嶋先生の活躍によるところがすくなくない。宿泊オリエンテーションは、野島の青少年研修センターを利用したが、宿泊設備はあるものの、食事の用意はなかったが、弁当ではかわいそうだというので、追浜のレストラン・エルシャンテに依頼してケイタリングで温かい食事を提供して貰うことになったこと、またその後、短大の近くの横浜市市民の森の宿泊施設上郷森の家を毎年使うことが恒例になったが、これらは、短大でのリトリートや宿泊オリエンテーションの経験が活かされた。
文学部に移籍したものの、わたしは、比較文化学科教授のまま、一方では短大国文科科長と兼務という辞令も貰っていたから、募集を停止した国文科の残務整理にもかかわることになった。この間、尽力いただいたのは、短大の教務課長、実質的には短大を切り盛りし、残務整理という労多くしてまた報われることのすくない仕事に関わっていただいた中村英夫事務次長である。
もともと、大学教員としてのわたしの生活は、山口県立女子大学(現山口県立大学)に専任講師として赴任した1976年から始まった。前年、県立の短期大学から昇格したばかりのこの大学には、最初の卒業生を出すのと同時に退職、早稲田に移られた杉野要吉先生の後任として八景キャンパスから移転したばかりの室の木校地の短大に移籍したのだが、図らずもわたしは、ここでも新しい学科の新設に関わると共に、40年の歳月を刻んだ短大国文科の閉鎖に立ち会うというめぐりあわせに遭遇することになったのだ。最後の学科長としてのわたしの念頭にあったのは、教員だけでなく、一人の学生も犠牲者にすることなく、国文科の歴史に幕を閉じることだった。卒業生にとって、かけがえのない思い出がぎっしり詰まった母校が終わりをつげることは、住み慣れた実家が新しく建て替わってしまうときに覚えるような寂しさを喚起する出来事であるに違いない。感傷といえばそれまでだが、わたしはそういう感情も大切にしたいと思った。結局、募集を停止してから2年間、単位を未修得の学生2名のために授業を開講、やはり国文科から人間環境学部に移籍した牧野ひろ子・岸正尚の両先生や、矢嶋先生などと共に未修得学生のために臨時の時間割を編成することになった。幸い、比較文化学科は新設して間もないため持ち時間はすくなく、わたしも短大キャンパスに文学部から通い、学生も熱心で未修得の単位を取得、同様の他学科の学生とともに、帆苅猛先生の司式のもと卒業式を行い、コーヒーとケーキで簡素ながら懇親会も行って前途を祝すこともできた。閉鎖するのは卒業生達に申し訳なく、残念でもあるが、国文科が、それだけでなく短大が学長の吉田博先生や宗教主任の帆苅猛先生、中村英夫事務次長などの尽力もあって、単位未修得の最後の一人が卒業するのを見届けて終了することができたのは、せめてもの慰めというべきかもしれない。
本文執筆にあたっては2002年7月22日発行『MEMORIAL関東学院女子短期大学―あの日・あの時―』発行者・中村英夫氏(元関東学院女子短期大学事務次長)の貴重な資料に助けられた。心からのお礼と感謝を申し上げる。 岩佐壮四郎
2025年4月
<岩佐壮四郎先生>
関東学院女子短期大学国文科 元学科長
関東学院大学文学部 元教授
関東学院大学名誉教授