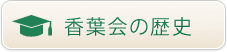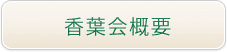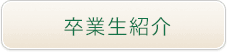追悼 中田 弘良 先生
岩佐壮四郎
■中田先生とは、中国旅行を共にしてから親しくなった。故岡松和夫、山口和子先生らのほかに、国文科の牧野ひろ子、伊東光浩の各先生も一緒だった。国文科では、中国からの私費留学生として梁愛蘭さんを北京の第二外国語学院から受け入れており、それが機縁となってできた同大学に、友好訪問するというのが目的だった。現在では当たり前の中国からの私費留学生だが、当時の中国と、高度経済成長のただなか、バブル直前といっていい日本との経済的格差は甚だしく、中国からの私費留学生などほとんどいないというのが実情だった。『日中日旅行社』という国営企業に勤めていた梁さんが日本に留学できたのも、彼女の一族がもともと横浜中華街で飲食店などを経営していた華僑であり、中華街で喫茶店「ブラジル」を経営していた叔母さん一家が身元引受人になって、女子短大に入学することになったのだった。このかんの事情については、岡松和夫先生の長編『海の砦』にも触れられている。
■中田先生は、北京ではなかなか人気者だった。人民大会堂前でも、北京の繁華街の王府井(ワンフーチン)でも、また、万里の長城でも、我が中田老師(ツォンテン ラオシー)の周囲には人だかりができた。二、三人がたちまち十数人になった。なかには先生に付いて歩く人々-いわゆるオッカケ-もでた。
中田先生は東京五輪(1964年)のレスリングの候補選手に選ばれたことはあったが、もちろん、有名人などではなく、長身のイケメンでもなかった。それどころか、身なりこそ日本人ふうだったが、中国人にしては背も低くずんぐりした、村夫子然とした、つまり中国の山奥からでてきた田舎者らしい彼にどこか魅力があるわけでもなかった。その中田老師(ラオシー)に、人民帽を被った中国人たち-当時はまだ文革が終わったばかりだった-に、どうしてゾロゾロついて歩く、オッカケもでてくるほどの人気があったのか。
それは、彼が一寸した魔法(マジック)をやったからである。むろん人々をペテンにかけたわけではない。■中田先生が、玄人はだしの奇術の技の持ち主であるのをご存知の人はすくなくないだろう。附属幼稚園のクリスマスで、自前の衣装でサンタクロースになった園長さんの中田先生は、手の平から、トランプのカードやハンケチ、チョコレートを取り出して見せては、園児達を夢中にさせた。■だが、中田先生が人々を虜にしたのは、ごく初歩的な手品だった。消えた筈の百円硬貨が、手からでてくるという、例のあの手品である。むろん、玄人はだしの彼の手から出てくるのは一個だけではない。二個も三個も出てきた、どういう細工をしたものか、この不思議な日本人(リーベンレン)の掌(てのひら)からは千円札まで飛び出してきたのである。改めていうまでもないが、当時の日本と中国の経済的格差は甚だしかった。万里の長城では、日本人とみると、「我是登上長城」と書いたTシャツを、十枚千円で売り付けようとする売り子たちが群がってきた。■それに、中田先生は中国語もできた。後述するように、彼は中国(満州)で幼少期をすごしたからである。
■成田からの帰りの電車のなかでは、四人掛けのグリーン車のボックス席で、満州時代の中田先生の思い出を、岡松和夫先生と山口和子先生と共に拝聴することになった。中田先生が中国語を話せるようになったのは、戦後になってからだ。中田先生は、満州国建国の翌々年の昭和10(1935)年生まれで、中国語(満州語)を話す必要もない植民地宗主国からの移住者の子弟として満州で育った中田少年は、それまでの恵まれた環境から突然、正反対の境遇に突き落とされた。その苦労話のなかでケッサクなのは、お母さん手作りの、甘い饅頭、すなわち牡丹餅(ぼたもち)を売り歩いたハナシである。
牡丹餅を売り歩くという境遇のなかで、いわば必要に迫られて覚えたのが満州語=中国語だった。学校で正規に学んだものではないが、混乱した旧植民地で、生き延びていくためのツールのひとつが、満州語=中国語だったといっていい。私たちが北京を訪問したのは、文革が終わり、鄧小平の改革開放政策がひとつの実りをあげつつあった-天安門事件の記憶は生なましかったとはいえ-時期だけに、街の空気にもひとつの開放感が漂っていたことは事実である。これも開放政策後に、夜の北京を彩り始めた屋台に立ち寄った際も、若い店主と、折からの、仲秋の月をめでながら、それこそ旧知の人のように、むろん遼寧省辺の訛りの強い中国語で談笑していた姿も忘れられない。■笑顔といえば、「中田老師(ツォンテン ラオシー)、中国雑技団に入ったらどうですか」と冗談交じりに問いかけたときに、中田先生の顔に浮かんだ我が意を得たりという笑いも、瞼に焼き付けられている。実際、彼=中田先生には、そのまま中国という人民の海に放り込まれても、そのまま、スイスイと環境に順応できるしなやかさがあった。レスリング、カヌー、手品、アコーデオンと中田先生は何でもできたが、それは器用であったからではない。それもあるだろうが、環境に適用しようという懸命な努力のたまものであったのではないか。
その少年の心を中田先生は生涯大切にしていた。今でも、「日本のボタモチいらんかね、美味しいよ」と、満州訛りのカタコトの中国語で雑踏を売り歩く九歳の彼の声が聞こえてくるような気がする。再見(サイチェン)、中田老師(ツォンテン ラオシー)!
中田 弘良(ナカタ ヒロヨシ)先生 略歴
1935(S10)年〜2025(R7)年
1961年 日本体育大学卒業 関東学院大学奉職
1978年 短大幼児教育科へ移籍 附属幼稚園主事、幼児教育科長を歴任
2002年 人間環境学部人間発達学科特約教授
2006年 関東学院大学人間環境学部名誉教授
2025年 2月21日逝去(90歳)
著者紹介
岩佐 壮四郎(イワサ ソウシロウ)先生 略歴
1946(S21)年4月18日生まれ
1969年 早稲田大学卒業
1976年 山口県立大学専任講師
1977年 早稲田大学大学院文学研究科博士課程
1979年 関東学院女子短期大学国文科奉職 図書館長、国文学科長を歴任
1998年 「抱月のベル・エポック」でサントリー文芸賞受賞
2002年 関東学院大学文学部比較文学科教授
2012年 早稲田大学博士(文学)授与
2016年 関東学院大学名誉教授